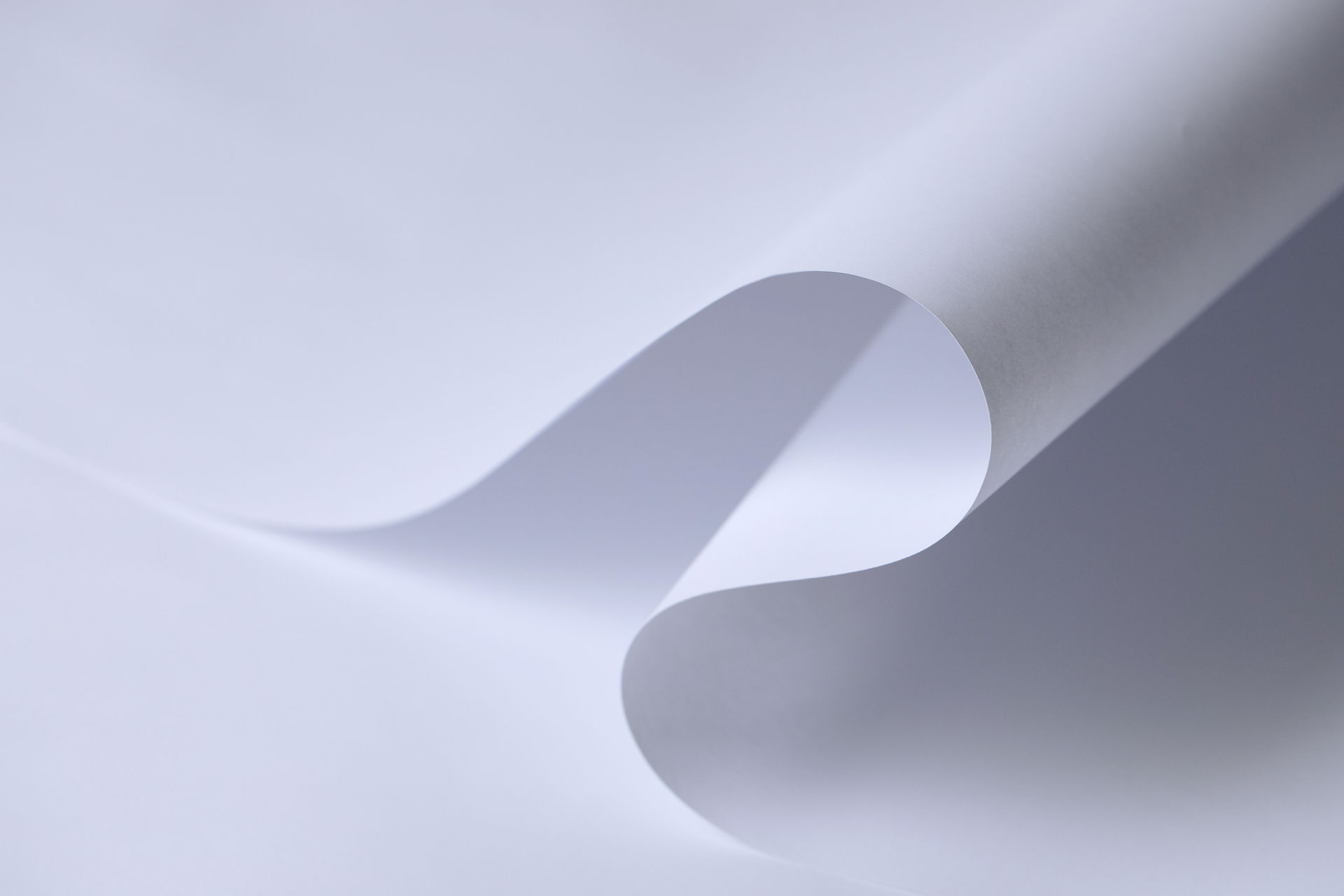
Cause and effect of the name
通年雪に覆われた大地の国、皇都イシュガルド。
この地は教皇と呼ばれる者により、代々政治が担われていた宗教都市国家だ。
国内は繁栄を極めているように見えたが、長きに亘りドラゴン族との戦いにより人々の暮らしは暗影を見せていた。
同じ国に住まう者も地位によっては虐げられ、弱き者はその日を生きる事さえ儘ならなかった。
俺はこの宗教都市国家で生まれた。
正確には「らしい」と言うことぐらいで、俺自身にその記憶はない。
こんな凍てつく寒さの中で生き延びられるのはある程度の地位に就くものか、それらの人々に従事する者くらいだ。
何の地位も名誉もない俺が、仮に今この地に居たとして…生きていられる保証など無い。
否…精々生きるために培ったこの腕が役に立つならば、夜盗ぐらいにはなれただろうか。
物心ついた頃には砂の都、ウルダハに居た。
そこで幸せな生活は無かった。
行商の父は自らの欲の為にご禁制のソムヌス香を売り捌き、母はそれに手を出して精神を病んだ。
温かな家庭はそこになく、後に父は不正取引により銅刀団により投獄された。
精神を病んだ母は手の付けようがなく、俺は生きる為に汚い仕事を請け負うようになる。
その金で母を医師に託す為に…。
「お前なんか産まれてこなければよかったのよ!あの女と同じ…卑しいフォルタンの血め!」
髪を振り乱し短刀を振り回す母を、俺はこの手で殺した。
フォルタン…この名を聞いたのはその時が初めてだった。
父だと思っていた男は本当の親ではなく、だからだろうか…記憶にある中で父、義父に優しくされた記憶はない。
むしろその瞳に、家庭に、俺と言う存在が居ないかのような…。
オッドアイの瞳さえ忌み嫌われていたのだから…。
「相変わらずここは寒いな」
クルザス中央高地に位置する砦。
キャンプ・ドラゴンヘッドと呼ばれる場所は、イシュガルドの四大貴族…フォルタン家が管轄する場所だ。
訪ねた人物は生憎不在で、俺はキャンプの一角にある扉を叩いてその人物へと片手を上げた。
温かな暖炉の前で読書に耽っていた人物は、俺を見るなり深くため息を吐き捨てる。
「いらっしゃい、よく来たわね。オルシュファンは不在よ」
小首を傾げた女性がパタリと本を閉じ、手招きして暖炉を指さす。
温まれと言うのかと思えばそうではなく、薪をくべと言う事らしい。
客人に仕事をさせるのだから、貴族と言うのは大概男女関係なく傲慢な生き物なのだろうか?
「知ってる…コランティオが首振ったからな」
「あら、そう。たまには彼と代わってお仕事してみたら?当主なら手当ぐらい出してくれるわよ」
新しい薪を暖炉に投げ入れ、背後でクスリと笑った女性に「あのなぁ」と不満を投げる。
「俺はオルシュファンじゃねぇんだよ。いくら似てるからって、俺とアイツのスタイルはてんで違うの…」
「素性は似たようなものでしょう?顔もよく似てる…。母親が姉妹だけあるわね」
そう、俺の母親とオルシュファンの母親は姉妹。
母親姉妹も義母姉妹で、俺の母はシェーダーの生まれ。
だから俺もシェーダーの血を持って生まれてきたんだ。
唯一オルシュファンと違う点は、俺が妾の子ではないと言う事。
フォルタンの一族に嫁いだ母から生まれた血族。
しかし、俺が生まれて間もなく…フォルタン家に事件が起こる。
当主であるエドモン・ド・フォルタン伯爵の下に、非嫡出子が誕生してしまったことだ。
貴族でも大貴族に当たる一家に生まれてはならない子が誕生したことで、その余波は血族にも波及した。
生まれたばかりの俺と共に、母は家を追い出された。
姉妹と言うだけでその後のフォルタン家に影を落とす存在になる…。
降りしきる雪の中、何処かの地へ生き延びられればフォルタンの名を忘れよ。
命尽きれば、深き雪が親子を覆い隠してくれるだろう。
けしてクルザスの地に足を踏み入れるな…、忌まわしき大地にその血を容れるな。
「その選択が間違っていることなど、誰だって判っている。それでも当時のイシュガルドではそれがまかり通ってしまったのよ」
「別に、アンタを責めてる訳じゃないさ…ニヌ夫人」
消え入るようなか細い声で「ごめんなさい…」と呟いた女性もまた、フォルタン家の血を引く血族。
俺がこの地に初めて足を踏み入れた時、真っ先に俺を見て名を呼んだのだ。
誰も知らないはずの、俺の、本当の名を…。
「過去がどうであれ、俺は生きてて今ここにいる。出て行けと言うなら出ていくし、アイツを待てと言うなら待ってるさ」
正直…俺はこの地が苦手だ。
いつ来ても寒いし、人は冷たいし、信用に値する人物を探す方が苦労する。
知らぬ者が居れば「異端者」だのと決めつけ審問にかけられそうにもなったし、実際かけられた訳だ。
正直者が馬鹿を見るこの地に救いなど必要ないだろうと…。
だけど、キャンプ・ドラゴンヘッドだけは違った。
衛兵の中には疑いの目を向ける者はいたが、それを上司であるオルシュファンは許さなかった。
冒険者がこの地で貴重な存在であることもそうだが、外からの存在を受け入れるこの場所は、閉鎖的な皇都の人間とは考え方が違う。
その時々で何が正しいのかを理解している。
何よりも、オルシュファンと言う男の器の大きさに救われたのだ。
だから俺は————
「ここに居たか!コランティオからお前が来ていると聞いたので探したぞ、シュー!」
勢いよく開け放たれた扉の向こう、目を輝かせて両手を広げた男は、雪を被ったまま俺をぎゅっと抱きしめる。
ホーバージョンから伝わる冷気にぐっと胸を押し返し「冷てぇな」と抗議すれば、男は声を上げて笑った。
「ハハハ!すまんな、久方ぶりの来訪だろう?お前が来ると分かれば、皇都へ使いを出したものを…。待たせたな」
「お前の仕事なんだろうが…部下に押し付けないでしっかりやれよ」
「ふふ、お前は本当に真摯だな。荒くれ者だと言っていたが、私はきちんと理解しているよ。誰かを犠牲にしてまで自分を優先する奴ではない、とな」
「…褒めちぎっても、何も出ねぇよ」
俺はこの地が苦手だ。
だけど…こいつは、オルシュファンだけは好きだ。
俺を分かってくれる、唯一の…。





